2020/6/1
CEOメッセージ 新型コロナウイルスを契機にホワイトカラーの生産性倍増を目指す
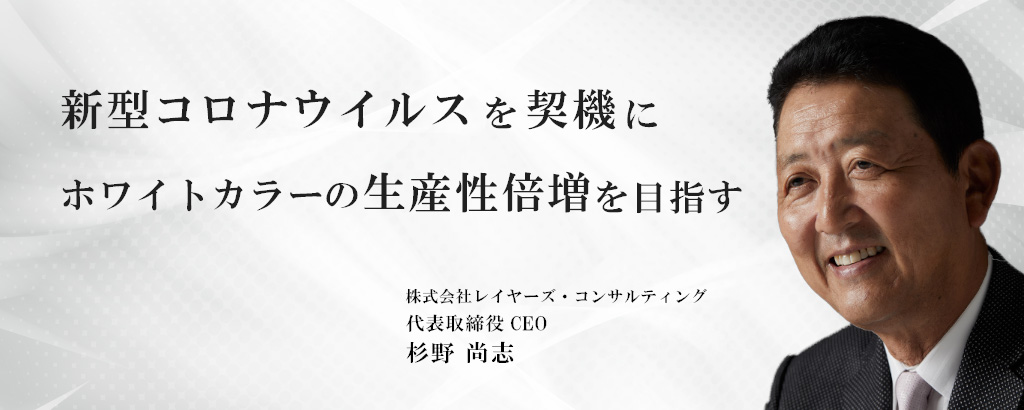
新型コロナウイルスの感染拡大によって、私たちの働き方は否応なしに変化の時を迎えました。私たちは目の前の危機を乗り越えると同時に多くの気づきを得て、よりよい働き方と多くの成果を手にすることができると信じています。
当社代表取締役CEO杉野より、特に生産性の低いと言われているホワイトカラーについて、これを高くする働き方の実現に向けて当社での実践事例を踏まえ提言したいと考えております。
新しい働き方への予感~オンライン飲み会で分かったこと~
本音を言うと、「オンライン会議やリモートワークでは、社員の生産性が悪くなるのではないか」と抵抗感がありました。
ところが、いま流行りのオンライン飲み会に参加して、「新しい働き方が拓ける」と予感しました。
オンライン飲み会はせいぜい30分で飽きてきて、長くても60分で終わってしまいますが、時間が長くない割に意外と面白く、「またやってみたい」という不思議な感覚を覚えます。
一人ずつ話すので、論理的に話そうと心掛ける人が多く、話が錯綜せずに会話がスムーズに流れました。結果的にいい意味で感情の高ぶりがなく、心地よいコミュニケーションが取れたのです。
生産性倍増
半分の時間で終わるオンライン会議の実践
オンライン会議は、映像やマイクの性能上、大声で話さないと通じない感覚があり、立ったまま行う会議と同じく1時間以上続くと疲れてきます。
弊社では、経営会議を含め多くの会議を2時間で行っていましたが、今は1時間以内でオンライン会議を実施しています。
最初は慣れないため準備不足が目立ち、1時間以上かかってストレスを感じながら実施しておりましたが、感情的議論が少なくなり論理的思考が優先し有効な結論が出やすく、今では非常に有益な会議を実施できていると感じています。
1時間の制約の中で、創造的議論をするために、以下の3つの実践ポイントが重要と考えております。
ポイント1:事前準備
1時間以内で会議を終わらせつつ、品質を担保するためには準備が非常に重要となります。
事前に資料を配布し参加者全員がきちっと目を通すことが必須です。
オンライン会議では出席者全員の顔が画面に映っているので、何も発言しない人は非常に目立ちます。
何も発言しない人は会議に出る価値はない、という考え方から出席者には必ず発言をしてもらいます。
発言が苦手な人もいますので、その意味でも準備が必要です。
ポイント2:リアルタイム思考、論理・データ思考による会議運営
会議の運営ではまず時間を厳守することが重要です。
議長と司会役を定め、司会役はタイムキーパーの役割を果たし、議長はアジェンダに沿って結論付けていきます。
必要な情報をその場で画面上に次々映していき議論を深めていくことが必要です。
「後で調べます」「後で報告します」は禁句です。
オンライン会議ではリアルタイム思考、論理・データ思考をデジタル技術を使ってフルに活用することが重要です。
また、議事録をその場で作成しリアルタイムに確認、合意をとっておくことも重要です。
ポイント3:インフラシステム・インフラデータの整備
会議の場でリアルタイムに情報を引き出し有効な議論をし、また効率よく事前準備をするためには、経営インフラシステム及びインフラデータが必要不可欠です。
弊社では、未だ不十分ですがプロジェクト管理、営業プロセス管理、顧客管理、利益管理、人事管理システムなどを活用し、何とかリアルタイムでの意思決定をしたいと考えております。
オンライン会議で最も良くないのは結論を先延ばしすることと、不確かな情報に基づく曖昧な意思決定です。
リモートワークによる執務の飛躍的生産性向上
リモートワークには以下の特質があると考えます。
- 通勤・移動時間が無く、時間を有効活用できる。
また、突発作業、雑務が無いので集中して効率良く作業ができる。 - 途中でちょこちょこ聞いたりすることができないので、インプット、アウトプットをしっかり定義して仕事をする。
- このため、成果に対して最短で達成するために時間を意識するようになり、執務時間が減る(平均6時間勤務)。
- 結果として、会社で準備不足の中でダラダラ仕事するよりも、はるかに生産性が上がる可能性がある。
→60%以上の人がリモートワークを続けたいと考えている(日本生産性本部調べ)
しかしながら、これはメリットの側面を言っていることであり、普通にリモートワークをしてしまうと生産性はアップするどころか単純・定型的作業のみ行う集団となってしまいます。
→80%以上の人は生産性が変わらないもしくは下がっている(Unipos調べ)
従って、リモートワークで生産性を上げるためには以下が重要であると考えます。
- 指示される人のランクに沿ったインプットとアウトプットを定義する。
・インプットとして必要データと作業手順を指示する
・アウトプットは具体的な成果物のイメージを明確に指示し曖昧なまま進めない - 時間を自己管理する。
「今日中(8H単位)」はやめて「午前/午後(4H単位)」、さらに2H単位で自己管理する。 - 途中で分からなくなったら、遠慮なく上司及び同僚に相談する。
言われた上司は嫌がらずにその場ですぐに指示し、解決する。
必要な場合は、プロジェクト外の人にも協力を仰いで検討する。
プロジェクト外の人も嫌がらずに参加する(協働意識の強化) - そのためには執務時間中はオンライン会議はつなぎっぱなしにしておく
現在、コンサルティングワークはほぼ全てリモートワークで行っております。結果として、生産性は落ちることなく執務時間も今までの60%になっております。
まだまだ改善の余地はありますが、新しい働き方による飛躍的な生産性向上の手ごたえを感じております。
まとめ
生産性倍増のためのキーポイント
ポイント1:完全成果主義への移行
時間やプロセス、進捗は自己管理し、会社は成果物を事前にきちん定義して成果物でその人の業績評価する。
ポイント2:リアルタイム思考、論理・データ思考の徹底
従前のホワイトカラーは優秀であればあるほど忖度思考に陥り、リスク思考が強いあまり、その場で結論を出してしまうのを嫌う傾向にある。
新しい働き方では徹底したリアルタイム思考、論理・データ思考に基づいたスピーディかつ適正な意思決定をすべきと考える。
ポイント3:インフラシステム・インフラデータの整備】
新しい働き方改革においては、インフラシステム及び社内外のデータがなければ、仕事になりません。もしインフラが整っていない企業がリモートワークに移行すると効率が悪化し、大失敗に終わるだけです。
ポイント4:自己管理+協働体制の構築
他人の目がない環境だからといって自己管理ができなければ、これからのビジネスパーソンとして不適格だと言わざるを得ません。
その上で、利他の精神に基づく協働体制の構築が必要です。
困ったことがあれば、「15分、20分ください」と願い出て、上司や同僚とディスカッションをしたり、時には部署外のメンバーに助けを借りる場面も出てくるでしょう。
これは相談する側は遠慮なく相談し、相談を受ける側も嫌がってはいけません。
大変厳しい新型コロナイルスの災害を逆にチャンスとして捉え、最も生産性が悪いと言われている日本のホワイトカラーに対し、生産性倍増を目指すべきと考えます。