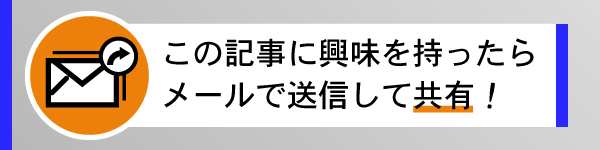重荷の固定費を溶かして絞り出せ
会社のコアコンピタンスに必須でない業務や機能は、極力減らしたいとどの経営者も考えています。その方法も一度は訊いたことのあるやり方です。ところが上手く行っている会社とそうでない会社があります。その違いは何でしょうか。
今回は、固定費を外部化したり、変動費化、DX化するときの要諦を紹介します。
固定費が重荷
約3年も続いたコロナ禍もようやく終わりを迎えようとしています。しかしこの3年の中で企業はコロナ禍に身構えて縮み込み嵐を過ぎるのを待っている間に、減らしにくい固定費率が高まり、経営の重荷になってきています。営業部門が苦労しているにも拘らず、本社管理部門は人員体制を守られており、赤字の元凶のように感じます。何故でしょうか。
それは売上が落ちても人数は変わらない、他社との差別化に役立っていない、誰でもできる付加価値の低い仕事をやっていると感じられ、しかも固定費と言いつつ売上が上がると固定費も増加するからです(一方向の固定費)。
従って、出来れば減らしたい、変動費化したいと感じる経営者は多いのではないでしょうか。
ここでいう固定費は、費目でいうと
① 人件費
② 設備関連費
部門では、
③ 間接部門(経理、総務・人事労務【本社部門、工場・支店など】、法務)
④ 購買部門
⑤ 生産部門(コモディティ化した製品を低価格で生産)
⑥ 営業事務部門
が当たります。
固定費が小さくなり、かつ忙しくなったら直ぐに稼働して素晴らしいアウトプットを出して!と望む経営者がいらっしゃいますが、そのような魔法の手はありません。あるのは皆さんが既に知っている手段です。しかし手段はその使い方で上手くも下手にもなるのです。
手段には、業務のアウトソーシング(BPO化、派遣社員等の活用による変動費化)とDX化です。
それらを上手く使いこなすポイントを述べていきましょう。
固定費対策その1:固定費の外部化
では、固定費を圧縮するにはどうしたら良いでしょうか。会社として必要な業務機能である限り全くやらないわけにはいきません。従って、自社の社員がやるのではなく、外部に委託する(BPOの活用または外部人材の活用)かDX化するかです。
外部委託(BPO化)を上手にするためのキーポイント
BPO市場は年々拡大しており、その傾向は今後も続くと予想されています。では上手くBPO会社を使うにはどうすれば良いでしょうか。そのためには外部に委託するとしてもキチンと準備を行い、効果が出るのを見極めてから外部化する事が必要です。それを怠ると再度内製化したり外部化先を変更したりするにも簡単ではありません。
1.業務を外部委託する部分はいつでも戻せるように準備せよ
通常の外部委託業務によくある業務の例
経理系業務では、記帳代行、経費精算、固定資産計上・償却費計算など
人事系業務では、勤怠管理、給与計算、社会保険手続き、採用・入社手続きなど
① 社内に残す機能との切り分け
何を社内に残し、何を社外に出すかを決定します。
通常、経理業務では方針の決定に係る事項は社内に残します。例えば、会計基準の選択、借入方針、管理会計などです。これら以外の単純処理業務を外部化します。
人事業務では、採用方針、評価基準の考え方、昇給率などです。これらの方針を検討する人材が社内に必要です。これら以外のやり方が決まっている手続き系の業務を外部化します。
② BPOとのインタフェース設計
・記帳代行:仕訳入力に必要な領収書や請求書、銀行通帳の記録などを渡すことで帳簿等の記帳を行い、決算及び青色申告に必要な帳簿の整備をしてくれるサービスです。この場合、必要証票をBPO先に渡すタイミング・方法・保管方法を決めておきます。また、出来上がった帳簿と証票類はいつ返還され、会社はどうやって保管するかを決める必要があります。
・社会保険手続き:社員の社会保険基金・組合等への入会・脱退の手続きをBPO会社に委託します。会社は社員個人とのやり取り、給与計算への反映がなされるよう経理BPO先へ連携を行います。
③ 文書化
既存の業務フロー上でBPO化する範囲を記述します。担当部門ごとにインプット情報、BPOでのプロセス、BPOからのアウトプット情報を記載します。
BPOに委託したプロセスの内容は、BPO先が使っているシステムも含めてなるべく詳細に記述しておくことで、他のBPO先への変換や、自社での再内製化の時に役に立ちます。ある意味での業務プロセスの社内蓄積です。
2.BPOアウトプットをチェック
BPO先に業務を委託しても任せきりではなく、自社内でチェックを行います。特に委託した当初はミスはBPO先でも起きますし、チェックする事で緊張感が生まれ、ミスの発生も防げます。
3.国内BPOの活用
これまでの中国などの海外でのBPOもコストアップとなってきており、コミュニケーションギャップや品質の問題、また業務内容を海外に知られてしまう恐れもあります。そこで当社では株式会社ベルシステム24と共に国内BPO拠点である株式会社Horizon Oneを設立、国内で広い範囲にわたって業務を請負っています。そこではコミュニケーションスキル及び法令・業務についての知見があるベテランが多数在籍しており、安心して業務を委託できますし、余計な説明時間も発生しません。
今後は品質や情報セキュリティの面からこのような国内BPOがさらに増えていくと予想されます。
固定費対策その2:固定費の変動費化
1.派遣やアルバイトの活用
単純業務を外部化する方法には良く知られた派遣やアルバイトを使う手もあります。この場合は社員が業務指示やアウトプットのチェックをする必要がありますので、BPOよりも業務品質の担保はありません。その代わりコストが安いというメリットがあります。
派遣やアルバイトを使う時のポイントは、良くできる人を長く使うことです。たとえ途中で業務が空く時期があったとしても、他部署の仕事を回すなどしてその人材を確保した方が良いでしょう。一度契約が空いてしまうと同じ人材を確保できる保証はありませんし、優秀な人ほどその可能性は低いと覚悟すべきです。
また派遣社員に任せた業務を文書化することも大切です。やり方を人に依存させず、他の人にも業務移管するのを容易にします。職務表や業務プロセスを作成するのと同様です。これはノウハウの蓄積や職務給の元になる職務定義にも通じます。
2.社員のマルチタレント化と繁忙期に合わせた人員配置
特に複数業務を経験してきたベテラン社員には、業務の整理・体系化に貢献して貰うと共に、それらの業務のお助けマンになって貰い繁忙期に合わせた人員配置をします。これはいくつかの会社ではチャレンジしています。そこでの成功のポイントは手伝ってもらう側の感謝の念と、手伝う側のプライドを如何に維持するかです。季節労働者のようではなく、ピーク時に合わせて各現場を助ける友軍としての位置づけと評価制度が鍵を握ります。
固定費対策その3:DX化の推進
DX化の進め方については他にも多くの方が述べているのでここでは多くを述べません。DX化という言葉が囃し立てられて既に何年かが立ちますが、上手く行っているケースが増えたとは思えません。何故上手く行かないのでしょうか。
幾つかの理由はあるでしょうが、まず第一にユーザ部門とシステム部門の双方が相手方に多分の期待をしていて、やるべきことにギャップが生まれているからではないでしょうか。
良くありがちなのは、ユーザ部門は「自分たちはシステムのことは分からないので希望を言えば、あとはシステム部門が上手くやってくれる」と考え、システム部門に丸投げして終わり。システム部門は、「業務のことは良く分からないので、ユーザが言うとおりに作れば文句は出ない筈だ」で、業務やビジネスは理解する必要はないと考え、言われたままに作成すれば良いとし、全体から見て無駄なことがあってもそのままにして開発を行う。
こんなやり方では双方のコミュニケーションが正しくできる筈もなく、結果として出来上がったシステムは会社が望む形にはなっていません。会社として多大な投資をしているにも拘らず効果が得られず、業務担当の誰かさんの要望を形にしたシステムが稼働するだけです。
このようなケースを回避するには、ユーザ部門、システム部門が双方の仕事を理解するステップが必要です。小さな部分から着手し、双方の理解が進み、より多くの範囲が理解できた段階で、その範囲のシステム化の絵を双方及び会社の経営層が納得するまで検討し、机上シミュレーションで検証しながら進めることです。これによって人も育ち、後からの改修もしやすくなるでしょう。これらがDXリテラシーを高める方法でもあるのです。外部の専門家もそれに役立つように活用すべきです。
当社もユーザと一緒になってRPAの導入・POC方式によるシステム開発や会社としての要件検討などをお手伝いしています。
日本でのDX化は欧米に比較して遅れており、世界デジタル競争力ランキング で日本は23位です。アメリカが1位、2位はシンガポールとなっており、3位以下は欧州勢が多くランクインしています。しかも、韓国が10位、台湾が13位、中国が22位となっており、日本はアジア勢と比較しても遅れているのがわかります。
今後の人手不足や競争力に直結するDX化は企業の存亡に係わると言っても過言ではないでしょう。
今回は、固定費を流動化・縮小化する方法として固定費の外部化とDX化をご紹介しました。詳細については是非お問合せください。



 ソリューションに関する
ソリューションに関するオンライン相談問い合わせる メルマガ登録
最新情報をお届け! メルマガ登録
職種別ソリューション