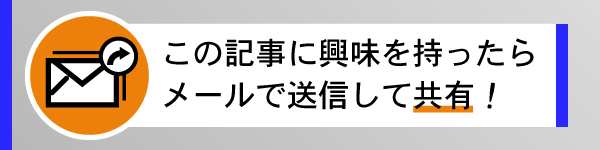漂流DXからの脱却
~正しい人材を船に乗せ、乗せたら降ろすな~
難易度の高い航海(=全社としてのDX)でも着実に船を前進させるには、どのような工夫が必要なのでしょうか。
何がDXの成否を分けるのか
「DX」という単語が当たり前のように使われるようになって久しい昨今の世の中で、流石にDXを単なる「システム導入」「システム化」と捉える考え方は減ってきています。少なくとも、「データ化・システム化を検討する上で業務自体も変革しなければならない」ことは標準認識になったように見えますが、だからといって、残念ながら日本企業でのDXの成功率が大幅改善しているというわけではありません。統計やデータは様々ありますが、いずれも成功の比率は10.0%前後と極めて低い数字で発表されています。
何がその成否を分けるのでしょうか。改革・変革の要素は大きく「戦略・計画」「組織体制」「実行手法」の3つと言われますが、これらのどこに改革の成功を左右するポイントがあるのでしょうか。今の時代、DXの実例や手法に関する書籍やセミナー・研修は数知れず、ある程度、戦略の立て方や実行手法は確立・共有化されてきているといえます。そうだとすれば、問題となってくるのは、誰がそれをやるか、社を代表して推進する役割を誰に担わせるのか、その組織作りこそが重要なポイントといえるのではないでしょうか。
貴方が経営者で、会社をあげたDXを今こそ推し進めたいと考えているとします。貴方はどのような組織を設計し、社内の誰をどうアサインするでしょうか。
「重要なのは現場の声」という安易な発想
昨今、改革の担い手である「DX人材とは」に関しては「DよりもXが重要」という声が多いように見えます。「X」とは変革を進める能力を指し、周囲を巻き込み、組織を変えようとする意欲や推進力がDX人材に求められる、という論調です。
実際に多くの企業では、過去に業務効率化施策や新規システム導入を推進した経験のある中間管理職をリーダーにプロジェクトチームを立ち上げています。そして「業務と言えば現場」発想で、営業業務に詳しい人材、会社を変えたいと意気込む若い現場社員、といった基準でメンバーを選定している例が多くあります。
こうしたプロジェクトチームでは、まず自由に「現状の業務における非効率」や「あるべき将来の業務」等をテーマにブレストを行い、そのあるべき姿と現状業務とのギャップを「課題」として設定…といった流れで序盤は非常に活気ある議論が行われます。このまま順調に検討が進むかと思われますが、課題を具体的に認識した頃から、勢いが落ち、アウトプットが出なくなってきます。まるで荒波に飲まれ針路を見失った船のように進みが頼りないものになるのです。
こういった事例は世の中に多く見られますが、何が要因なのでしょうか。
実際に、改革の頓挫を経験した企業の関係者はこのように言います。
「業務をデジタルに置き換える話が具体化した途端、メンバーからは『本当にデジタルで代替できるのでしょうか。こんなシステムわたしたちに使えるのでしょうか』とリテラシーの低い発言が出てくる」「チームリーダーですら『システムは完璧なんでしょうか?入力したデータのチェック業務を無くして大丈夫でしょうか』と逃げ腰になってしまう」
【図1】漂流DXの典型
安直なアサインが招く残念な認識違い
チームの失速の要因はメンバーのデジタルリテラシー不足、という単純な話なのでしょうか。表面的にはそう見えますが、問題の真因は、彼らを船に乗せる、その時点で発生していると考えられます。「現場の意見を聞かせてほしい」「業務に障らない範囲で良いので参画してほしい」等、安易な推薦文句で、そのメンバーの処遇や主要ミッションを見直すこともなくアサインしているのではないでしょうか。そしてそのやり方が、多くのメンバーに誤ったマインドを植え付けているのではないでしょうか。
- 責任範囲の誤認
-自分は「業務改善のための」要員で「デジタル化の」要員ではない
-デジタルやシステムのことはわからなくてもその導入は他の誰かが主導してくれる - 責任の重さの誤認
-自分のミッションはあくまで営業でプロジェクトへの貢献は二の次
-デジタルの理解が薄く検討に貢献できなくても自身の評価には響かない
2つの誤った認識で参画したメンバーは、自身は業務の変革に現場の視点から実現可能性等のコメントを提供する立場で、デジタルに関する知見・意見は求められていないと思い込むことになります。その程度のモチベーションで参画した結果、検討の内容がいよいよシステム導入や業務の自動化に及んできた途端、「これ以上は自分の守備範囲外」という意識にかられ、打ち合わせで意見を言わなくなり、酷い場合は本来業務で忙しいからと打ち合わせすら休みがちになります。そしてそうなっても、「業務に触らない範囲」を保障してしまった経営は当然咎めることはできません。こうしてチーム全体が勢いを失っていくのです。
「まず自分が変わる」人材だけが組織を変える
デジタル化が致命的に遅れていると言われる日本企業にとって、DXプロジェクトは、企業の体質自体を大きく変える取組みです。そのようなプロジェクトに現場から人材をアサインするには、従来のプロジェクトアサインよりも一段上の戦略・工夫が求められます。
それは、「会社を変える」と意気込む前に、まずは「自分自身が率先して変わる」意識を持ってもらうことであり、その意識を持ちうる人材を正しく選ぶことです。現場で営業など従来業務に邁進してきた人材にとって、デジタルは縁遠く、難易度が高い分野であることが殆どです。その領域に挑戦し、未知の知識を習得することに意義を感じる人材でなければ、「デジタルへの苦手意識」を克服できず、最終的に検討から脱落します。脱落者が多い場合、プロジェクト自体も当然頓挫してしまいます。
「DX人材に必要な『X』」とは、「『自己変革』力」だと捉えるべきなのです。
そうした前向きなマインドを持ちうる人材を見極め、育成することは、当然経営者の責任であり、具体的には、2段階の仕組みづくりが不可欠となります。
ステップ1:マインドセットの仕組み
- 「業務視点でなくDX人材として期待している」ことをアサイン時に経営として伝える
- 真にマインドセットに応じてくれる人材を見極める体制・仕組みを構築する
ステップ2:マインドが持続する仕組み
- メンバーがスキル装着とプロジェクトの推進に時間を避ける環境・ルールを整備する
- プロジェクトの成果をメンバーの人事評価へ反映させる制度を構築する
【図2】DX推進に不可欠な2段階の仕組み
DXの真の担い手~自己変革を促すもの
こういった仕組みづくりはプロジェクトの成功確率を高めるうえで非常に重要であり、中でも、DX人材としてのマインドを持ちうるメンバーの見極めがキモだと言えるでしょう。
メンバーを公募制にして面接時に意思表明させる、データ・システムに関する事前学習とテストの合格をプロジェクトチーム参画の条件とする、等々企業によって選抜方法に工夫は見られます。ただ、DX検討に真に適している人材かどうかは、そもそも自身が携わるDXの目的をどう捉えているかによって見極められると考えます。
それは、あくまで顧客満足を高めることが目的と認識し、社内ではなく顧客ニーズを起点に変革の必要性と変革ポイントを捉えることのできる人材です。よくありがちな、現場の非効率改善を求める声ばかりを集めることに答えはなく、一見自分たちにメリットはなさそうな顧客の立場からの要望・不満をニュートラルに受け止めることに意義があるという考え方が重要であり、不可欠なのです。
このような捉え方のできる人材の多くは、「できない」言い訳でなく「どうすればできるか」を考える習慣を持ち、改革を自組織のみで無理にやり遂げようとして施策を行き詰まらせることもありません。自社で解決しない部分は、そのスキルを有する外部のパートナーの協力を柔軟に受け入れ、自身の視野も広げながら変革を実現に導こうとします。正しいメンバーを船に乗せ、乗せ続ける仕組みさえ整えば、一隻の船(自社)だけで航海を乗り切る必要はないのです。
このように、従来通りの思考を超え、新しい解決策を考え出せる人材こそ、真のDXの担い手であり、その原動力は根底にある徹底した顧客視点だと考えられます。
【図3】真のDX人材とそうでない人材との違い
関連サービス
#デジタル化戦略・ITマネジメント


 ソリューションに関する
ソリューションに関するオンライン相談問い合わせる メルマガ登録
最新情報をお届け! メルマガ登録
この記事の執筆者
-
 岸本 直子事業戦略事業部
岸本 直子事業戦略事業部
マネージャー
職種別ソリューション